肉の種類
⑴ 次の図を見て、1~8までの肉の部位の名前をいいましょう。
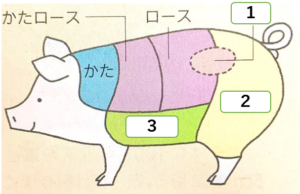
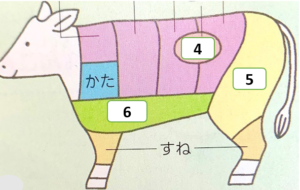
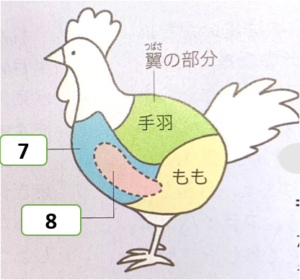
⑵ 肉の鮮度の見分け方について、( )に当てはまる言葉を入れましょう。
① 豚肉・・・艶のある淡い( A )色で、脂身は( B )色のものが良い。
② 牛肉・・・鮮やかな( C )色で、赤身と脂身の境目が( D )しているものがよい。
③ 鶏肉・・・透明感のある( E )色で、皮の毛穴に( F )があるものが良い。
④ 肉全般・・・嫌な臭いがしない、( G )が出ていない、弾力がある、ぬるぬるしていない、ものがよい。
⑶ 肉を柔らかくする働きがある食品を2つ答えましょう。
⑷ すね肉のような筋の多い肉は、どうすると柔らかくなりますか。また、どのような料理に向いていますか。
⑸ 肉を焼いたときに変形しないように、筋を切ることを何といいますか。
⑹ 肉の栄養素を3つ答えましょう。
⑺ 肉を加熱するとたんぱく質の変成によってどう変化しますか。
⑻ 肉を焼くときに、肉のうまみを逃がさないための工夫として、火の加減をどうするとよいでしょう。
⑼ スープなどを作るときに、肉のうまみを汁に出すための工夫として、どう加熱するとよいでしょう。
答え
⑴ 1=ヒレ
2=もも
3=ばら
4=ヒレ
5=もも
6=ばら
7=むね
8=ささみ
⑵ A=ピンク
B=白い
C=赤
D=はっきり
E=ピンク
F=凹凸
G=ドリップ
⑶ パイナップル・ショウガ・はちみつ等
⑷ 長時間加熱する。(たんぱく質の一種であるコラーゲンが分解されて柔らかくなる)
ビーフシチューや煮豚など
⑸ 筋切り
⑹ たんぱく質、脂質、ビタミン
⑺ かたくなる。
⑻ 最初は中火~強火で焼いて、ある程度焼けたら弱火にするとよい。
⑼ 水から長時間ゆっくり加熱するとよい。
魚の調理
⑴ 次の文章の( )に当てはまる言葉を入れましょう。
食用になる魚の種類は多く、肉質の違いから、白身魚と赤身魚に分けられる。白身魚は、(A)が少なく、味が(B)で、生は(C)いが(D)するとほぐれやすくなる。赤身魚は、生では柔らかく、(D)するとかたくなります。また、産卵に備えて(E)を体に蓄積する時期があり、その季節は脂質含有量が多くなる。魚の脂質は、血液中の(F)値を下げ、心筋梗塞、脳梗塞を防ぐ効果があるといわれている。
⑵ かつおには旬が2回あります。春先にとれるかつお、秋に取れるかつお、それぞれ何といいますか。
⑶ 魚の鮮度の見分け方について、( )に当てはまる言葉を入れましょう。
切り身・・・全体に(A)があり、身、(B)、肉、皮に透明感と艶がある。(C)がたまっていないもの。
1尾の場合・・・(D)は澄んでいて透明感があり、外に張り出している。えらがきれいな(E)色をしている。(F)がはげていない。
⑷ 魚の料理について。煮魚をつくるときに火を通す時間はどうすると水分が保持され、煮崩れしにくく、美味しくなるでしょう。
⑸ 次の文章の( )に当てはまる言葉を入れましょう。
魚の臭みを消すには、
・(A)水や(B)水で洗う
・(C)を振ってしばらく置き、出てきた水分をふき取る
とよい。
⑹ 下の写真は、魚の下ごしらえについての手順です。🔲に当てはまる言葉をいれましょう。

答え
⑴ A 脂質 B 淡泊
C かた D 加熱
E 脂肪 F コレステロール
⑵ 春先=初がつお
秋=戻りがつお
⑶ A 弾力 B 血合い
C ドリップ D 目
E 赤 F うろこ
⑷ 短時間で火をとおす。
⑸ A 冷 B 酢 C 塩
⑹ 1=うろこ 2=内臓
3=ぜいご 4=えら
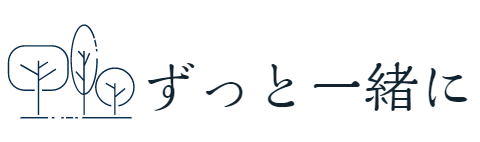
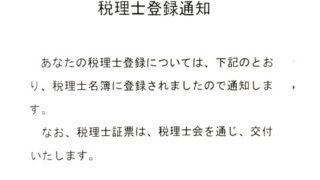


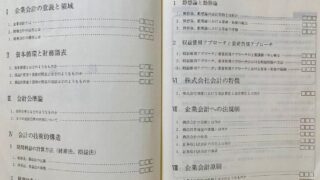
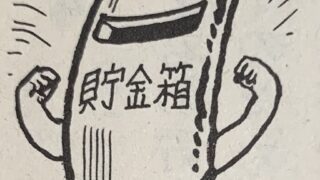


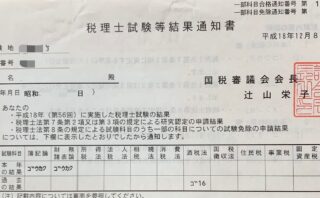
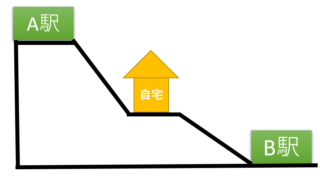
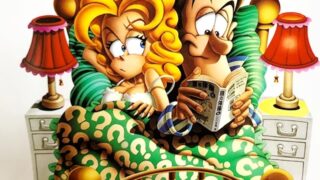








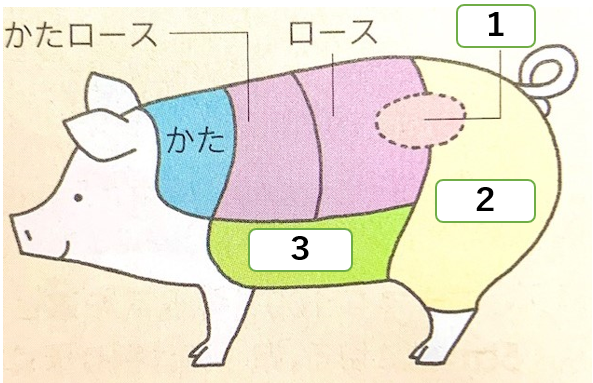



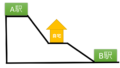
コメント